中学受験の三種の神器の一つとして名高いプリンター。
苦手な問題をコピーして弱点補強ノートを作ったり、テスト問題をコピーして見直ししたり、問題集をコピーして何度も解いたりと…受験生にとってプリンターはなくてはならない存在です。
我が家にもプリンターはありますが、国語も算数も問題集に直接書き込んでいたので、プリンターの必要性を感じていませんでした。
ただ、新4年生になってから、プリンターの必要性を実感するように。
特に理科と社会。
社会は地図系の問題。
理科は実験や考察問題などで、書き込み式のものが出てきたことからです。
これまで答えはノートに書いていましたが、さすがに地図や実験の類は難しい。
しかも、春期講習では「テキストに書き込んで」と先生からの指示があり、家での反復学習が難しくなってしまった!
事前にスキャンしておけばよかったと後悔したものです。
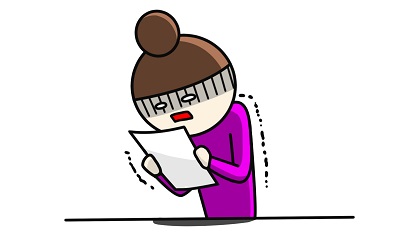
というわけで、我が家でも本格的にプリンターの導入です。
ただ、プリンターと一言にいってもさまざまなタイプがありますので、受験勉強に合わせたタイプで選ばなければいけません。
たかがプリンター、されどプリンター。
プリンター選びで勉強効率も変わるのですから、お値段だけで選べないのが辛いところです。
中学受験や日々の家庭学習で使うプリンターを選ぶ際のポイントは2つ。
①A3サイズの印刷が可能
②コピー、スキャナー機能が搭載されている
中学入試問題は、B4やA3サイズであることがほとんど。
塾のテストなどでも、B5サイズやB4サイズのプリントをホチキスで留めて出すスタイルは珍しくありません。
見開きで使うのもあるので、そうなると実質B4、A3サイズに。
6年生になると取り組むことになる過去問については、本番サイズに拡大コピーして解くのがいいとされています。
過去問集にはコピー倍率が明記されているのもそのためです。
本番よりも小さいサイズでやっていると、余白の少なさからも省略してしまう癖がついてしまう事もあるのだとか。
また、塾からもらうテキストやプリント、テスト用紙の量は膨大で、管理するのが大変。
丁寧にファイリングしても、1年前のテキストは開くことはなかなかない。
でも、捨てるのはためらわれるとして、どんどん溜まっていくという恐怖のループ状態に陥りがち。
収納をスッキリさせるだけでなく、閲覧・検索を簡単にするためにもスキャナー機能が搭載されているのが便利です。
データとして保存し、必要があればその都度プリントアウト。
ファイル名に塾の授業カリキュラム名や日付を入れておくと、探しやすくなります。
ちなみに、スキャンは授業が終わった後にするのがポイント。
データ化を習慣化することで、その週にやった学習ポイントなども振り返ることができます。
スキャンできれば、プリント整理も簡単で部屋の一部を圧迫することもなくなります。
問題と答えがバラバラになったり、1回分が行方不明になったりといったプリント管理問題も解消です。
テキストをどんどんスキャンしてデータ化したら、捨てる!
空いたところに地図や辞書、図鑑などを置く方が空間の有効利用になります。
さらに、あると便利なのが「自動原稿送り(オートドキュメントフィーダ:ADF)」。
束になったテキストをセットするだけで、自動で表裏スキャンしてくれると大変便利!
一枚ずつセットする手間もありません。
受験前もしくは終了組のご家庭に遊びに行くと、そこには必ずといっていいほどコピー機能のあるプリンターがドドーンとあるほど。
実際にプリンターを使っているママさんからはこんな声が…
「うちは必須よ(サピックス生ママ)!持っていない方は知らないわ。
(上のお兄ちゃんが)6年生の時は紙を大量に消費して、コピー用紙が追い付かなかった…(泣)」
「我が家は最初はA4サイズだったの。
でも、A3サイズのコピー機にすればよかったと後悔して買いなおした。
見開きで絶対に印刷できないし、半分に折って印刷するのが面倒」
「うちは5年生の後半で買ったんだけど、もっと早くに買っておけばよかったと後悔しているよ…」
話を聞いていると、「ブラザー」が人気のよう。
ちなみに我が家はエプソン。
今日からさっそく、プリンター生活開始です。
どんぶり勘定型の母にどこまできちっとできるか疑問ですが、山のように放置されているプリント類よりかはマシでしょう。
すでにカオス状態なので、早めにやらないと収集がつかなくなりそうです。







